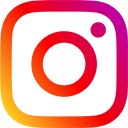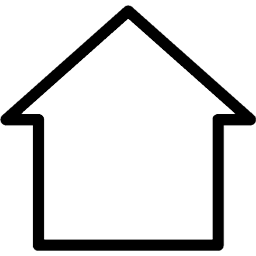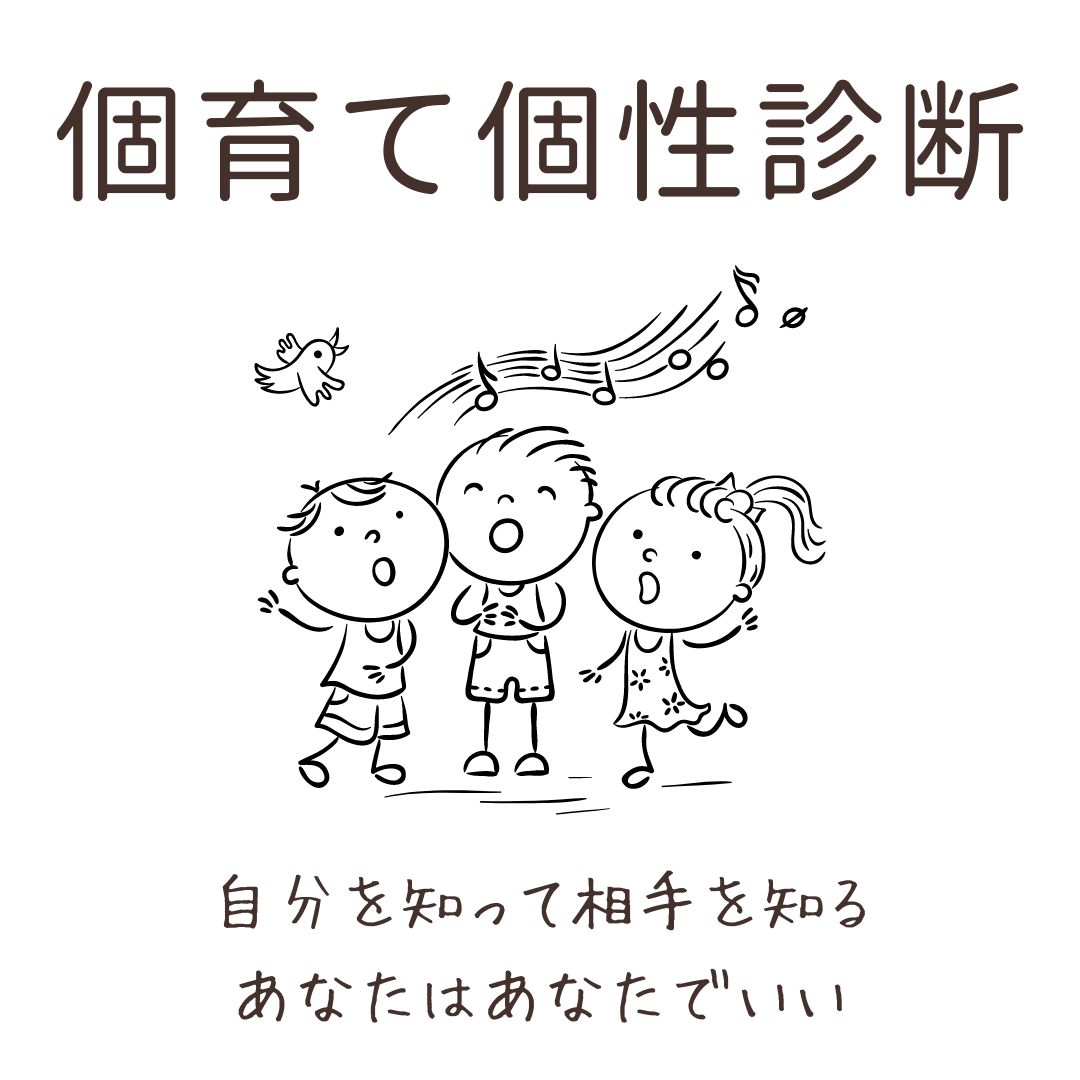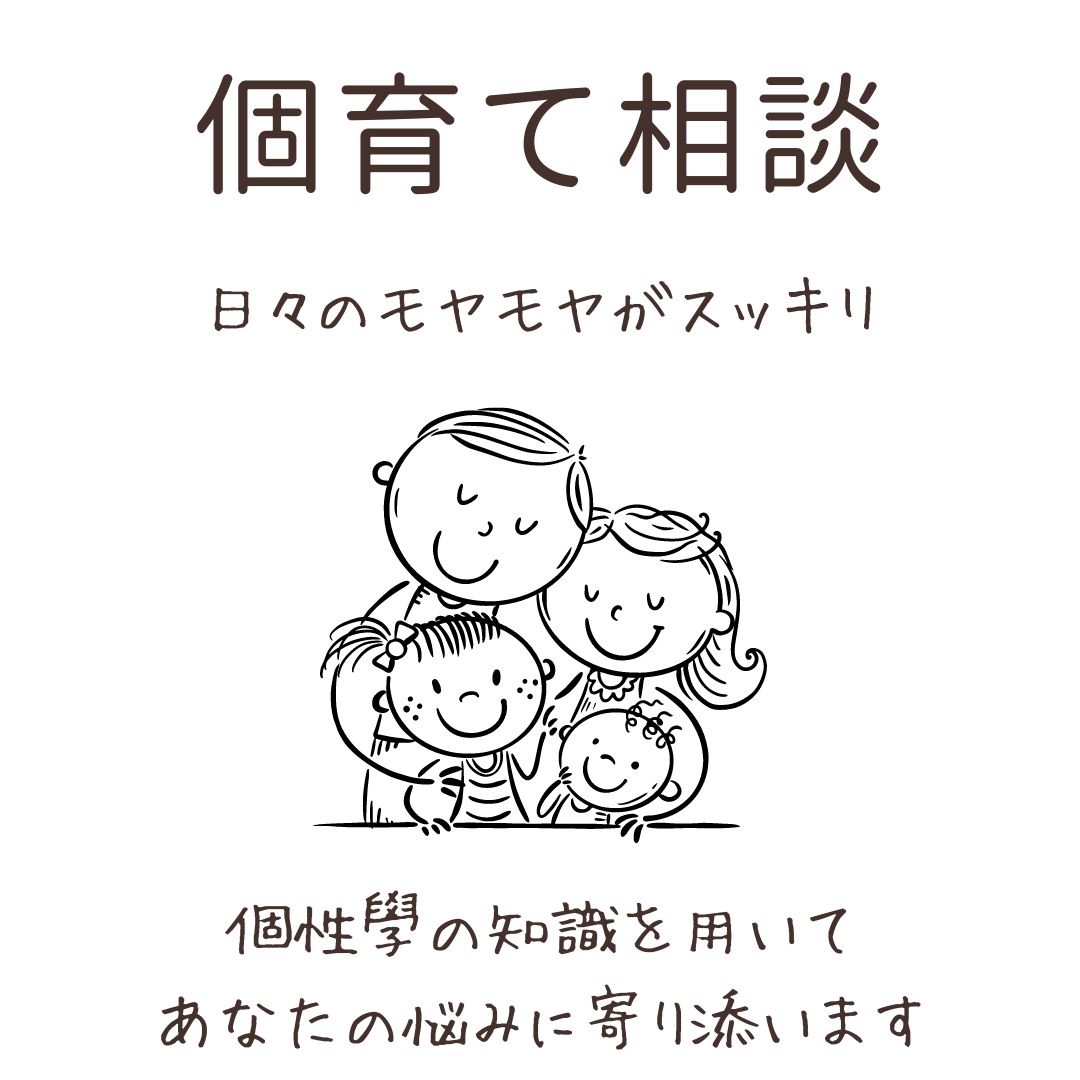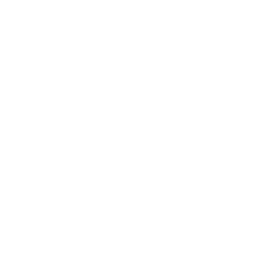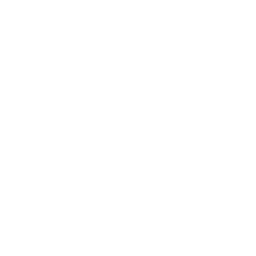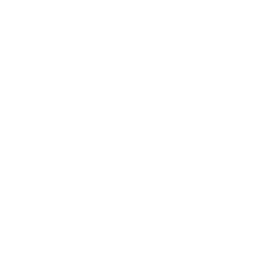新年度、学校に行きたくない子にできることー個性に合わせた関わり方と背中の押し方ー
こんにちは、個性學パートナーの土屋美保です。
このブログでは、
「仕事も子育ても、もっと私らしく楽しみたい」と思いながらも、
毎日の忙しさやイライラで、つい自分を後回しにしてしまうあなたへ。
こころの土台をやさしく整えるヒントと、
親子の“個性”を活かした関わり方をお届けしています。

「うちの子、甘えてるのかな…?」
「行きたくないって、ただのわがまま?」
「他の子は行けてるのに、どうしてうちだけ?」
そんなふうに思って、朝からついイライラしてしまうこと、ありませんか?
そしてあとで「私の対応は良かったのかな?」って、心配になる日もあると思います。
でも実は、「学校に行きたくない」と感じる子の中には、
ただ“慣れるのに時間がかかるタイプ”の子が一定数います。
新年度の始まりは、大人にとっても子どもにとっても、
ワクワクだけじゃなく、不安や緊張が入り混じる季節。
それは「怠け」でも「弱さ」でもなく、
“安心を確認できてからじゃないと動けない”という、その子の生まれ持った特性かもしれません。
この記事では、「慣れるのに時間がかかる子」に対して、
どう声をかければいいのか、どんな関わり方が合っているのかを、
個性學という視点を通じてやさしくお伝えします。
今日のこの記事が、正解のない子育ての小さな気づきになれば、幸いです。

新年度は「新しい」がいっぱいの季節
新年度が始まり、少しずつ慣れてきたかなと思った頃にやってくるGW。
ほっとしたような、でもどこか気が緩むような、子どもたちにとってはちょっとした“リセット”の時期。
GWが終わると、運動会、試験……。
次々にやってくるイベントの波に、気持ちが追いつかないままどんどん進んでいきます。
小学生も、中学生も、高校生も、
新しいクラス、新しい友だち、新しい先生、新しいルール。
どれも“新しい”ものばかりのなかで、
ワクワクだけじゃない気持ちを抱えながら、
子どもたちも、日々頑張っています。
比べる必要がないのに、つい比べてしまう私たち
子どもたちも、新しいクラスや友だち、ルールの中で、
日々、自分のペースでがんばろうとしています。
それは、きっと私たち大人も同じ。
新しい季節の中で、それぞれががんばっているはずなのに――
気づけばつい、なにかと比べてしまう…。
「あの子はもう慣れてるのに、うちの子は…」
「他の人は楽しそうに見えるのに、私はまだ不安」
本当は比べなくてもいいものを、比べてしまうことって、ありませんか?
比べてしまうのは、きっと人間の性(さが)
それは、大人の世界だけじゃなく、
子どもたちの世界でも、きっと同じです。
比べたくて比べているわけじゃないのに、
気づけば心の中に“比べグセ”がしのびこんできます。
比べてしまうのは、きっと人間の性(さが)なんだと思います。
誰かと比べることで、
「今の私、これで本当に大丈夫?」と確かめたくなる。
「比べちゃダメ」と思えば思うほど、また比べてしまう。
そして、比べた自分を責めて、心がちょっと疲れてしまう…。
そんな負のループにはまってしまう人も、多いのではないでしょうか。
抜け出す第一歩は、受け入れること
だからまずは、比べてしまうこと自体を、否定しないことが大切です。
「比べている自分」を責めるのではなく、
「今、そう感じてるんだな」と、まずは受け止めてあげてください。
「どんなものさしで、なにと比べている?」
そう問いかけられるようになると、
比べていたはずの気持ちが、少しずつほどけてくるはずです。
そして、自分の“ものさし”に気づけるようになると、
自然と、自分にも、周りにもやさしくなれるようになっていきます。
それぞれが持っている『ものさし』
比べてしまうときに、忘れてはいけないことがひとつだけあります。
私たちは私たちそれぞれいろんな形の「ものさし」を持っているということです。
目盛りも長さも、使いどころも人によって違うもの
私たちは、それぞれにいろんな形の「ものさし」を持っています。
その「ものさし」は決してひとつではなく、そして、どれも同じ大きさでもありません。
たとえば、
「すぐにドキドキしてしまうものさし」を持っている子もいれば、
「あんまり気にせず動けるものさし」を持っている子もいます。
ある子にとっては“なんてことない場面”でも、
別の子にとっては、“ものすごく緊張する瞬間”だったりする。
目盛りが細かい人もいれば、大ざっぱな人もいる。
1cmが「すごくこわい」人もいれば、
「なにも感じない」人もいる。
だからこそ、自分の持っている「ものさし」だけでものごとを判断することは、
ときに、大切な気持ちや思いを見落としてしまうことがあるのです。
生まれ持った“個性”で、ものさしが変わる
この「ものさし」は、生まれ持った個性の分類によって変わります。
簡単にいうと、どこの部分の「ものさし」の目盛りが大きいのか小さいのかが、
個性の分類によって変わるということです。
要は、慣れるのに時間がかかるっていうことひとつにしても、
人によって、いやその人の個性によって、どのくらいの期間を要するかが変わります。
安心できる場所を探している個性を持っている子と、
新しい環境が大好きな個性を持っている子とでは、慣れる時間やスピードが違います。
そして、持っている「ものさし」が違うから、
見えている「ものさし」も違うっていうことを私たちは忘れてはいけないのです。
子どもには子どもの、ママにはママの『ものさし』がある
ものさしは、
「このものさしがいい‼」
「このものさしがいいから子どもに持たせたい‼」
って選ぶことができず、生まれたときから持っているものです。
生まれたときから持っているものは、『個性學(こせいがく)』で分かります。
生まれたときから持っている特性が分かると、自分が持っている『ものさし』、
そして、子どもが持っている『ものさし』が分かります。
新しい環境になれるまで時間が掛かる子も、
ちょっと神経質になってしまう子も、
不安がる子も、
それもその子の特性です。
そして、
新しい環境になれるまで時間が掛かってしまうママも、
子どものことが心配になりすぎて不安になってしますママも、
心配すぎて小言が多くなってしまうママも、
それもそのママの特性です。
『行きたくない』の一言の重みは、個性によって変わる
生まれ持った個性の特性によって、
慣れるのに人より時間がかかる子がいます。
そして、それをちゃんと口に出せる子と、
口に出せない子がいるのも確かです。
同じ言葉でも、その子の背景・特性で意味が変わる
『学校に行きたくない…』
の一言も、
その子によって重みが違います。
それは、生まれ持った個性の特性だけで判断しかねる問題です。
でも、ひとつだけ、私が言えることは、
『学校に行きたくない…』の言葉だけで、判断しないことだと思います。
特別扱いでも、突き放しでもなく、“ちょっと時間がかかるだけ”
個性の特性は確かにあるものです。
あるものですが、
あるからといって、ダメなものでも、
ハンディになるものではありません。
ちょっとだけ、ストレスがかかりやすかったり、
時間がかかるだけ。
なので、腫物として扱う必要も、
特別視する必要もないのです。
『学校に行きたくない…』という言葉に、
すぐに「行かなくていい」と決めつけたり、
逆に「我慢して行きなさい」と押し返したりすることが、
この子の気持ちをちゃんと受け取ることには、つながらないのかもしれません。
あなただからこそできることがある
では、どうすればいい?
それは、子どもの個性に合った方法で、
子どもの背中を優しく押してあげることだと私は思います。
そのためには、
子どもの話を聞く必要だってあるし、
子どものことをよく観察する必要だってあります。
『不安』だったら、
なにが『不安』なのかを聞いてあげてください。
そして、『勇気』がでる言葉かけをしてください。
最後に、がんばっていった子どもを、
受け入れてあげてください。
頑張ったら、休める場所が必要です。
それが、子どもにとっては家で、
そして、心を許せる人、甘えられるのは、
子どもたちにとってはママです。
環境になれるのに時間が掛かる子は、
あまり掛からない子に比べて3倍の時間が掛かると言われています。
ということは3倍ストレスが掛かっているということです。
新年度が始まり、新たな環境で過ごす子どもたちに、
私たち親ができることは、
だた、ひとつです。
充電できる居場所を作ること、
それが、なによりも大切なのではって思います。
ものさしは人それぞれ 見えている世界も人それぞれ
ものさしは人それぞれです。
そして、そのものさしは世界にひとつだけしかありません。
私が見ている世界は、
私のものさしで見ている世界です。
あなたにも、あなたのものさしがあり、
お子さんにも、お子さんだけのものさしがあります。
みんな、見えている世界、
感じている世界が違って、
それはそれでいいのです。
自分がどのものさしを持っていて、
子どもがどんなものさしを持っているのかを知ることから始めてみませんか?

焦る日も、イライラする日もあっていい。
それでも、
「わたしはわたしでいい」
「あなたはあなたでいい」
って、思える子育てを一緒にしませんか?
自分や子どもの個性の分類がなにかが知りたい方は、公式LINEを登録して、**『個性』**とメッセージいただけたら、簡単な分類を無料でお調べします。
詳しい個性を知りたい方は、『個性診断』や『やさしい3分類講座』などの受講もオススメしています。
気になる方は、一度、気軽にお問合せ頂けたらと思います。
このブログが、あなたの心の土台を整えるきっかけになれたら嬉しいです。
いつもありがとうございます。