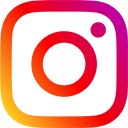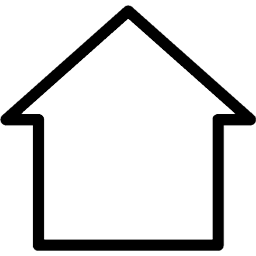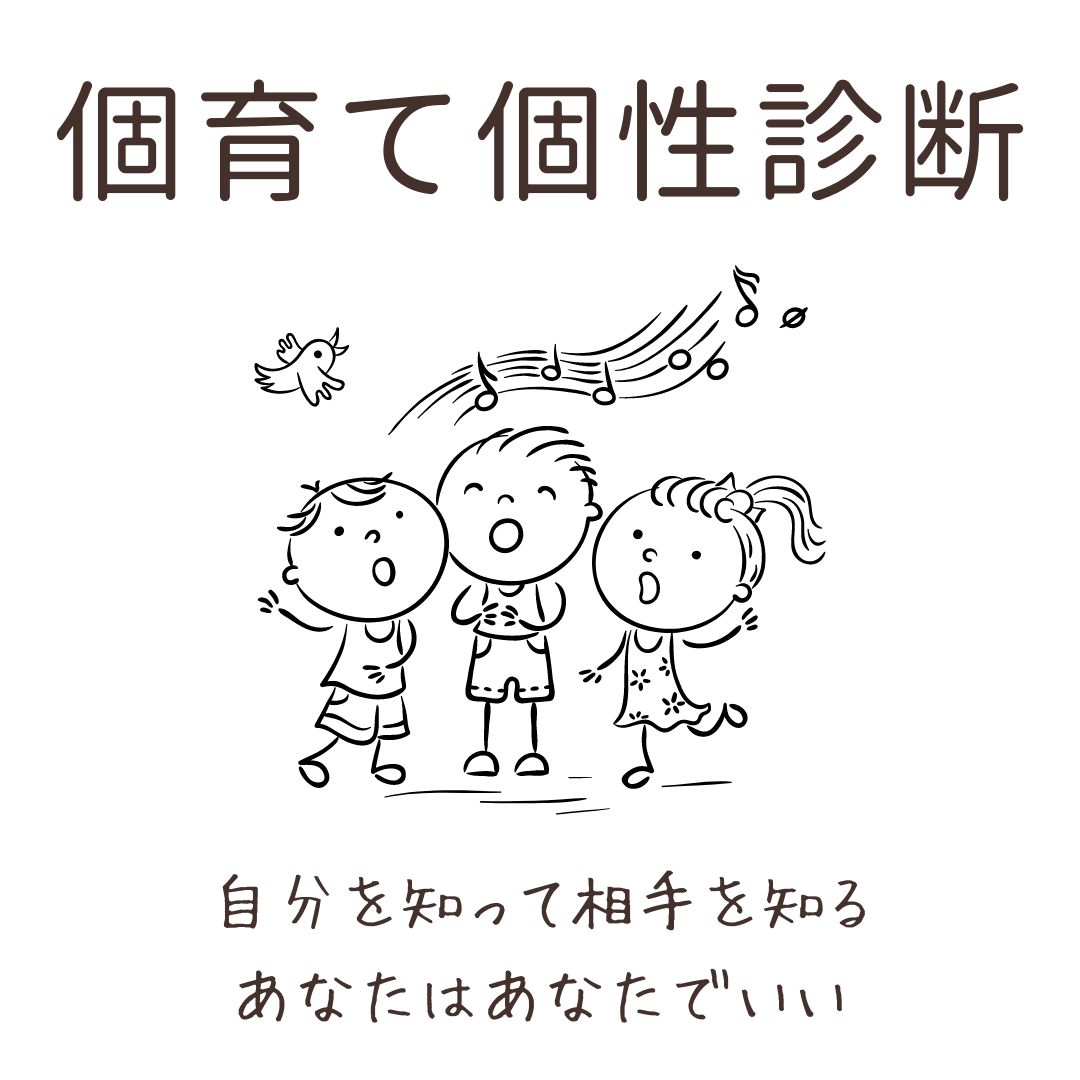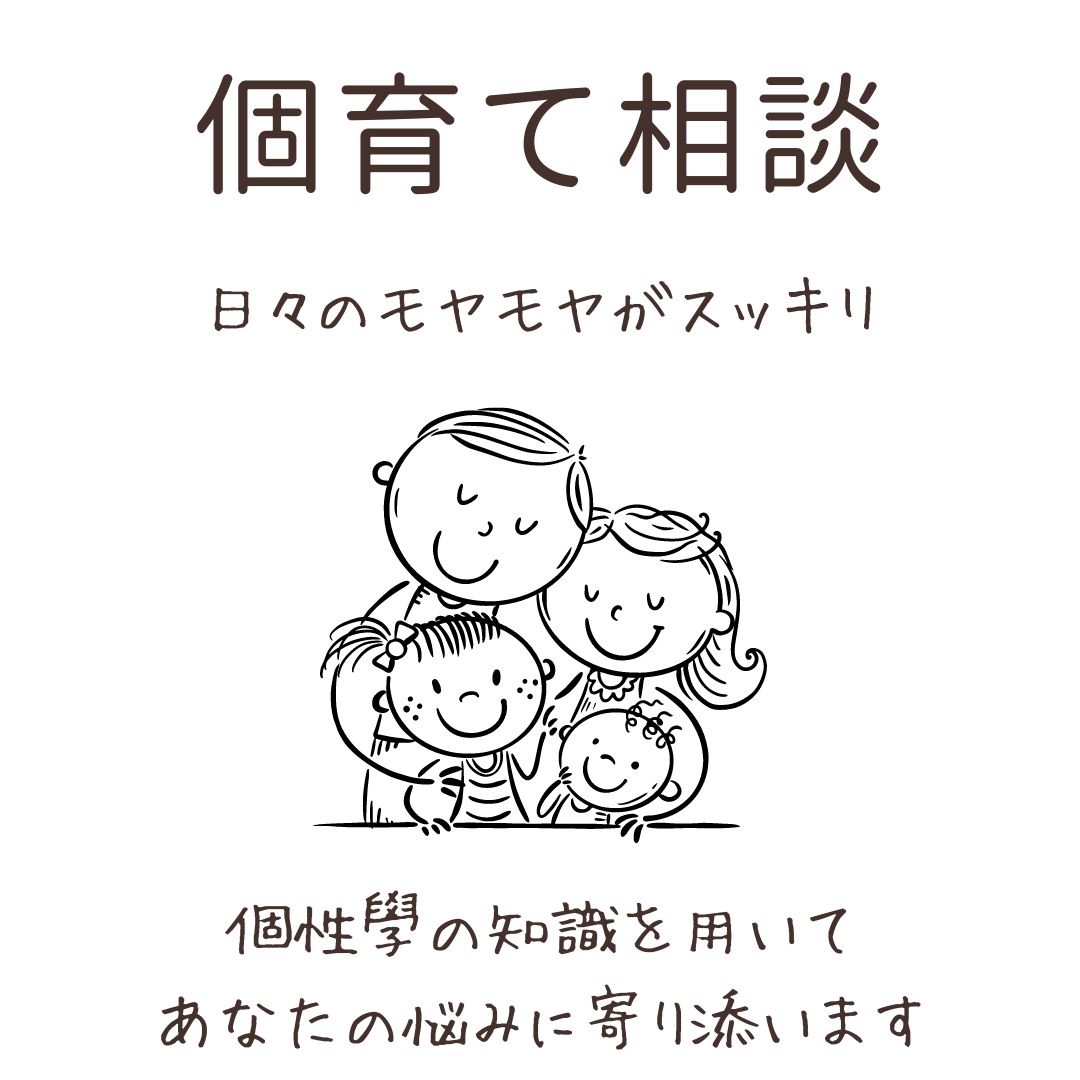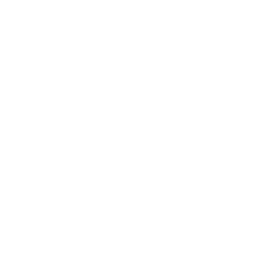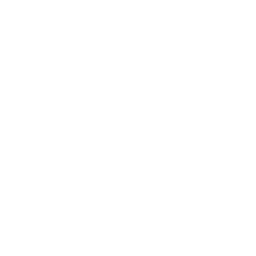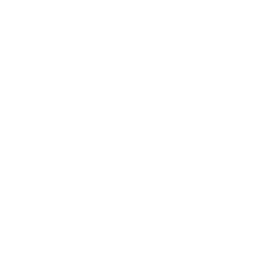【子育てから学ぶ個性學】「どうしてうちの子だけ?」悩んだ私が見つけた心の土台の育て方
「みんな違っていい」と頭では分かっているはずなのに、集団生活の中でわが子だけがみんなと同じことをしないのを見ると、心がザワザワするのは私だけでしょうか?
きっと子育て中のママの正直な気持ちのはずです。
私自身、保育園の発表会で、「ピョンピョン飛ぶ長女」と「一時停止したように固まる次女」という真逆の娘たちを見て、「どうしてうちの子だけ…」と悩み焦っていたころがありました。
ですが、娘たちの行動は「表現の違い」なだけで、その子の成長のエネルギーを削ぐ必要はないと腑に落ちたとき、私の子育てに「安心の軸」ができました。
今日のブログでは、ある意味個性的な二人の娘を育てた私が実践した「成長を信じるための2つの温かい声かけ」と、そこから得た「ママが安心できる子育ての軸」について、実体験を交えてご紹介します。
最後まで読んで頂けたら嬉しいです。
「どうしてうちの子だけ?」と悩んでいた私へ。真逆の娘たちから見つけた【ママの心が軽くなる答え】

先日、代休で休みだった中二の長女と一緒に、小5の次女の学習発表会を見に行って来ました。
一生懸命リコーダー吹いたり、歌ったりしている次女と、隣で目を輝かせながら妹を見ている長女を見て、私は、彼女たちが小さかったころを思い出しました。
私が仕事をしていたこともあり、長男も長女も一歳のときから、次女だけは少しだけ遅く二歳から保育園に通っていました。
長男は泣き虫な一面もありましたが、お遊戯会などではみんなと同じように踊ったり歌ったりができる子でした。
問題は、その下の娘たちでした。
みんなと同じを期待した私が戸惑った、真逆の娘たちの「本番での行動」
あの頃の私は、「どうしてうちの子だけ、みんなと同じことができないんだろう?」と、心の中で何度もため息をついていました。
まず、長女(当時3歳)。
私や家族の姿が目に入ると、そこからずっとピョンピョン跳ねるか、満面の笑顔で手を振ってくる。
もちろん、歌も踊りも関係ありません。隣の子が一生懸命歌っていても、彼女は手を振っているか跳んでいるかです…。
可愛いといえば可愛いのですが、あまりにそれが長く続くと、
「もうそろそろ歌ったら?」
「ちょっと止まろうか」と、つい小言が喉元まで出そうになります。
お遊戯会の話ではありませんが、保育園の参観日でのことです。
保護者も一緒に踊る場面で、「一生懸命踊ったら楽しいよ」という気持ちを伝えるべく、私は全身を使って頑張りました。
長女に視線を持っていくと、彼女は全然違う方向を見て、友だちと楽しそうにピョンピョンと跳ねていました(私の頑張りは長女の心に届きませんでした…)
とにかく、動きが止まらない。
まるで車輪を走り続けるハムスターのような子どもでした。
そして、次女のほうは、そんな長女とは正反対です。
運動神経も良く、やればなんでも器用にこなす子でしたが、参観日や運動会、お遊戯会など、普段とは違う環境では完全にキャラ変。
一時停止ボタンを押したみたいに少しも動かない。
「あれは次女そっくりの人形です」って言っても誰も疑わないぐらいフリーズ状態笑
「すごい静止力だ」とむしろ褒めたくなるほどでしたが、当時の私は、「みんなと同じことができない」娘たちを目の前にして、不安と焦りと怒りがミックスされたなんとも言えない気持ちを抱えていました。
そして、私は、なにも問題も心配もなくやることが出来ている他の子たちを羨ましく思う以上に、できないわが子のことを恥ずかしく思っていたのです。
個性學で腑に落ちた!「行動は違っても、根っこは同じだった」その理由

当時の私は、「みんなと同じことができない」娘たちのことで、心配で焦っているのに、表面では気にしていないフリを一生懸命していました。
そんな中で出会ったのが、「個性學(こせいがく)」でした。
この個性學では、人の個性には「内面」と「外面」という二面性があると考えます。
ざっくり言うと、内面は「基本的な価値観や意志決定をする部分」、外面は「その意志を行動に移す時の表現方法や第一印象」です。
そして、私と長女と次女は、「内面の個性」が全く一緒で、「外面の個性」が違います。
つまり、私と娘たちは、「思っていることは一緒」ですが、それを「行動として外に出す時の『表現』がそれぞれ違う」だったというわけです。
私たちの内面は、ちょっと人目がとても気になる繊細なメンタルを持っています。
なので、要は、人前で歌ったり踊ったりすることが恥ずかしいと思ったり、人の目が気になる指数が少し高めです。
そして、長女の外面は、やりたいことにはまっしぐらで止まらない。
次女の外面は、疑うから入る神経質タイプ。
なので、ピョンピョン跳ねる長女も、人形のように固まる次女も彼女たちが持っている個性からみたら不思議なことではありません。
母親の私の目からは、ジッとできない長女と動くことができない次女ですが、彼女たちは、ただ恥ずかしく、自信がないだけだったのです。
「だからと言って放置は違う」親がブレずに実践した2つの温かい声かけ
それが分かったからと言って、なにかが変わることは残念ですがありません。
だからと言って放置で、子どもたちが成長するのをただ待つのも違うと思います。
「個性」を知ることはとても大切です。
でも、それ以上に大切なことは、その子の心の土台を育てていくことです。
うちの娘たちは、「恥ずかしい」が強い子でした。
まだ3,4歳なので経験値が足りず、
「できる」「できた」「大丈夫」の経験体験が、「恥ずかしい」に負けていただけです。
これは、この個性だからの話ではなく、どの子でも通じる話です。
要は、「出来ていない」ことばかりに目を向けるのではなく、「できたこと」に目を向けて、しっかり褒める、そして認める、抱きしめる。
どの育児書にも書いてあることですが、本当にシンプルにこれだけで大丈夫です。
つい、心配して、子どものためにと思いアドバイスや、自分の精神状態によっては小言や注意になってしまうこともあるかもしれませんが、赤ちゃんではないけど、まだこの子たちは経験値がとても少ないです(ついもう3歳と思ってしまいますが…)
なので、「出来た!」っていう体験をいっぱいさせてあげることが私はなによりも大切だと思っています。
【私たちが実践した具体的な声かけの例】
🍀ピョンピョン跳ねてても、一瞬、歌ったらそこを褒める
🍀先生のそばを離れないけど、泣かずにそばにいたらそこを褒める
🍀そして、家に帰ってきたら、たくさんハグする
もちろん怒ることもありますが、お風呂時間や寝る前とかにいっぱいお話をする、ハグする、それを繰り返してきました。
で、うちの娘たちですが、年中さんの終わりごろ、だいたい4歳半ぐらいから、変わってきました。
長女は、年中さんのお遊戯会で、小さな声でしたが一人でセリフが言えたのがきっかけでした。
次女も年中さんだったと思いますが(やばい…3番目記憶が…)、なにかをきっかけに動き出しました。
そこから、彼女たちは、なにかあるたびに私の涙腺を刺激してくれてます。
振り返って思うことは、ただ一つ。
この子を否定せず、心の土台にエネルギーを注くことに集中して良かったということです。
親の役割は「比べないこと」わが子の個性を『認め、受け止める』親子で心の土台を育てていきましょう
いけないと分かっていても、私たちはついいろんなものと何かを比べてます。
どうしても、出来ていないことが気になって、焦ります。
それって、悪いことでもダメなことでもなく、親として、いや人間としてニュートラルな感情です。
だからこそ、一歩後ろに下がって物事を見れる余白が必要です。
親の私たちができることは、きっと、病名をつけることでも、諦めることでもありません。
その子の心の土台を育ててあげること、そのためには、自分の心の土台も一緒に育てていくことだと私は思います。
その心の土台を育てていくきっかけのひとつに、「個性學」で自分と家族の「個性」を知ることが
できます。そして、その「個性」を活かしながら、心の土台に水や栄養を上げることです。
「どうしてうちの子だけ?」と悩んだり、不安な気持ちになったりした時は、思い出してください。
あなたの温かい声かけこそが、わが子の「自信がない」という気持ちを溶かし、いずれ大きな成長へと繋がる「心の土台」になるはずです。
私の思い出話が、今、悩んでいるあなたの心が軽くなる、なにかしらのきっかけになれたら嬉しいです。

🍀今、公式LINEで無料プレゼント中🎁
ただいま公式LINEにご登録いただいた方に
『3つのメガネで見る個性のはなし』のPDFをプレゼントしています。
「わたしって、どんな人?」
「子どもや家族とうまくやっていきたい」
そんな方のヒントになる、“個性”の3つの視点をまとめたガイドです。
🍀30分の無料セッションを実施中♪
LINE登録後、【無料セッション希望】とメッセージを送っていただいた方には、
30分の個別セッションを無料でご案内中です。
あなたの中にある“モヤモヤ”を一緒に言葉にして、
「あなたらしさ」の軸を見つけてみませんか?
ご登録はこちらからどうぞ♪
下の画像をクリックしてくださいね↓↓

ピンときた方は、ぜひお気軽にメッセージください
じっくり自分と向き合いたい方には
✔無料個別セッション
✔個育てジャーナル相談
✔個育て個性診断
✔ 継続セッション講座
などもご案内しています。
気になる方は、お気軽にお問合せください。
いつもありがとうございます